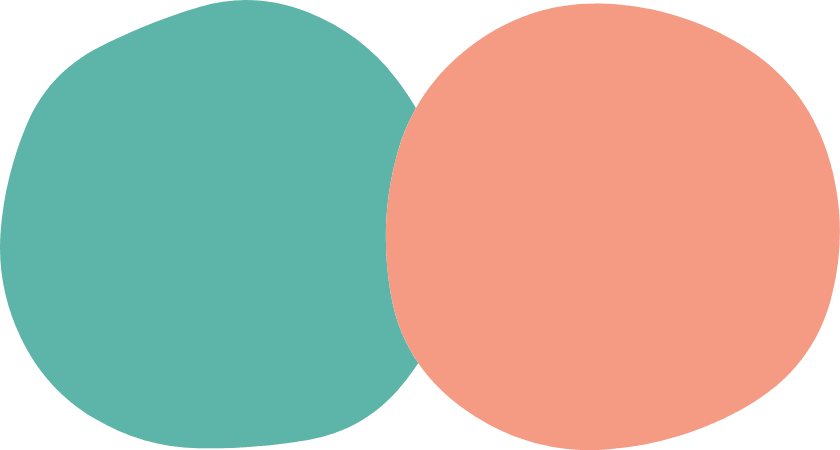生命保険は、相続税の節税になるの?計算式と注意点について!
相続税の負担を抑えたいのであれば、生命保険の活用を検討する方法があります!
生命保険は、保険の被保険者が亡くなった場合に、受取人に対して死亡保険金が支払われるものです。相続税の計算上、受け取った金額の一定額が非課税となります。
今回の記事では、相続税の生命保険の非課税金額の計算式と、活用時の注意点等について解説致します。
生命保険の非課税限度額は次の算式になります。
500万円×法定相続人の数
- 計算中の「法定相続人の数」の注意点
- 相続放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。
- 養子がいる場合は、法定相続人の数に算入する養子は次のようになります。
- 実子がいる場合は1人
- 実子がいない場合は2人
- 具体的な計算例
※生命保険の計算を分かり易く解説するため、ここでは、被相続人の他の遺産は考慮しておりません。- 夫が亡くなり、妻と子供(A・B)2人が法定相続人のケースで、妻と子供2人が500万づつ合計1,500万、死亡保険金を受け取った場合。
死亡保険金の受取合計が、非課税限度額500万×3人=1,500万以内であるため、受け取った保険金全額に相続税はかかりません。 - 上記と家族構成は同じで、子供2人(A・B)だけが1,000万づつ合計2,000万、死亡保険金を受け取った場合。
- 夫が亡くなり、妻と子供(A・B)2人が法定相続人のケースで、妻と子供2人が500万づつ合計1,500万、死亡保険金を受け取った場合。
-
-
- 保険金の非課税限度額は、1,500万
- 保険金の合計額は、2,000万
- 非課税となる金額
- 子供Aの非課税限度額計算 ①×1,000万÷②=750万
- 子供Bの非課税限度額計算 ①×1,000万÷②=750万
- 相続税の課税対象となる金額
- 子供A 1,000万-③=250万
- 子供B 1,000万-③=250万
-
按分計算して算出することになります。
生命保険金活用の注意点
- 契約内容により相続税ではなく、他の税目の対象となる場合があります。
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人の区分があります。- 契約者と被保険者が亡くなった人(夫)で、受取人が相続人(妻)の場合は相続税対象となります。
- 契約者と受取人が相続人(妻)で、被保険者が亡くなった人(夫)の場合は、一時所得となり、所得税・住民税の対象となります。
- 契約者が相続人(妻)で、被保険者が亡くなった人(夫)、受取人が他の相続人(子)だった場合には、妻から子への贈与税対象となります。
上記のように、契約内容により課税される税目が異なります。相続税の対象となる生命保険金(みなし相続財産)は、契約者と被保険者が同一の被相続人の場合ですので、注意が必要です。
- 相続放棄者や法定相続人以外は生命保険の非課税の適用を受けられません。
生命保険の非課税の適用を受けることができるのは、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)の場合です。そのため、死亡保険の受取人となっている場合は、相続放棄するかどうかを慎重に判断する必要があります。
相続放棄をしなければ、非課税の適用を受けられて相続税が発生しなかったのに・・・とならないように検討が必要です。
- 相続税納税目的の場合は、保険金の受取人を妻ではなく、子とする。
相続税の計算上、配偶者は税額軽減により、最大1億6,000万と配偶者の法定相続分のどちらか大きい金額までが非課税となります。そのため、一般的に配偶者が相続税を納税するケースは稀かと思われます。
配偶者の納税資金より、配偶者の税額軽減がない子供等の相続税の納税資金として、生命保険を活用した方が良いでしょう。
節税以外のメリット
- 保険金の受取を早期にできる
死亡保険金は、受取人の固有の財産です。受取人の単独請求により保険金が受け取れます。
預貯金等は、基本的に全ての相続人間での分割協議が終わらなければ引き出すことはできません。ということは、協議がまとまらなかった場合は、預金は凍結されたままとなります。亡くなった直後の葬式費用、医療費等の支払いに窮することも考えられます。
分割協議が不要な保険金受取により、金銭的な安心感を得ることが可能です。
- 相続税の納税準備資金にできる
相続税の納付期限は10か月です。分割協議がまとまらず、被相続人の預金が凍結されたままですと、納税資金は、相続人自身が準備する必要があります。さらに、相続税が多額だった場合には、納税をどうするのか・・・ということも考えなければなりません。
生命保険を活用することにより、納税についての不安がなくなり、余裕を持って、分割の話し合いができることにもなります。
まとめ
上記のように、生命保険を活用することにより、相続税の節税をすることが可能です。
また、節税以外にもメリットが大きいことが分かります。しかし、注意すべきこともあり、専門家に相談されて、検討加入されることをお勧め致します。